問1.(5)
以下の物が一般用電気工作物に該当します。
・600Vの電圧で受電している電気工作物
・出力10kW未満の太陽電池発電設備
・出力20kW未満の水力発電設備
・出力10kW未満の内燃力発電設備
・出力10kW未満の燃料電池発電設備
※風力発電に一般用電気工作物は無くなりました。
2023年から、小規模事業用電気工作物という枠組みができました。
・太陽電池発電設備
従来:50kW未満は一般用電気工作物
➡2023年~:10kW未満は一般用電気工作物。10kW以上~50kW未満は小規模事業用電気工作物
・風力発電設備
従来:20kW未満は一般用電気工作物
➡2023年~:20kW未満は小規模事業用電気工作物
解答の選択肢の一般電気用工作物に当てはまらない箇所に赤線を引くと、次のようになります。
(1)受電電圧6.6kV、受電電力60kWの店舗の電気工作物
(2)受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧200V、出力15kWの内燃力による非常用予備発電装置を有する病院の電気工作物
(3)受電電圧6.6kV、受電電力45kWの事務所の電気工作物
(4)受電電圧200V、受電電力30kWで、別に発電電圧100V、出力7kWの太陽電池発電設備と、発電電圧100V、出力15kWの風力発電設備を有する公民館の電気工作物
(5)受電電圧200V、受電電力35kWで、別に発電電圧100V、出力5kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物
以上より、(5)が答えです。
問2.(3)
作業者の資格と、認められる電気工事の作業は、次表の通りです。
| 作業者の資格 | 一般用 電気工作物 | 最大500kW 未満の需要設備 (600V超) | 最大500kW 未満の需要設備 (600V以下) | 非常用予備 発電装置 | ネオン工事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一種電気工事士 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 第二種電気工事士 | 〇 | × | × | × | × |
| 認定電気工事従事者 | 〇 | ||||
| 特種電気工事資格者 (非発装置工事) | 〇 | ||||
| 特種電気工事資格者(ネオン工事) | 〇 |
この表から、不適切な箇所は次のようにわかります。
(3) 第一種電気工事士は、最大電力250 kW の自家用電気工作物に設置される出力50 kW の非常用予備発電装置の発電機に係る電気工事の作業に従事できる。
以上より、(3)が答えです。
問3.(3)
電気設備に関する技術基準を定める省令
第五条 電路は、大地から(ア)絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は(イ)混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための(ウ)接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
以上より、(3)が答えです。
問4.(4)
電気設備の技術基準の解釈の第17条(接地工事の種類及び施設方法)の問題です。
接地抵抗値の規定は下表のとおりです。
| 条件 | 接地抵抗値[Ω] |
|---|---|
| 下記以外の場合 | \(\frac{150}{I_g}\) |
| 混触時、1 ~2秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を施設している | \(\frac{300}{I_g}\) |
| 混触時、1 秒以内に自動的に高圧電路を遮断する装置を施設している | \(\frac{600}{I_g}\) |
一線地絡電流\(I_g\)に関する規定は、
①実測値
②計算式で計算した値。ただし、計算結果は、小数点以下を切り上げ、2A未満となる場合は2Aとする。
\(I_1=1+\frac{\frac{V}{3}L-100}{150}=1+\frac{\frac{6}{3}20-100}{150}=0.6[A]\)
計算した値が2[A]を下回るので、接地抵抗値の式の\(I_g\)には、\(I_g=2[A]\)を入れて計算しますと、接地抵抗値\(R_B=\frac{600}{I_g}=300[Ω]\)
以上より、(4)が答えです。
問5.(5)
電気設備に関する技術基準を定める省令
第二十七条の二(電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止)
変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用により(ア)人の(イ)健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によって占められる空間に相当する空間の(ウ)磁束密度の平均値が、商用周波数において(エ)二百マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
以上より、(5)が答えです。
問6.(4)
電気設備の技術基準の解釈 第125条1項五号と、六号に関する問題です。
電気設備の技術基準の解釈 第125条【地中電線と他の地中電線等との接近又は交差】
低圧地中電線と高圧地中電線とが接近又は交差する場合、又は低圧若しくは高圧の地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合は、次の各号のいずれかによること。
ただし、地中箱内についてはこの限りでない。
一 低圧地中電線と高圧地中電線との離隔距離が、0.15m以上であること。
二 低圧又は高圧の地中電線と特別高圧地中電線との離隔距離が、0.3m以上であること。
三 暗きょ内に施設し、地中電線相互の離隔距離が、0.1m以上であること。
四 地中電線相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けること。
五 いずれかの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、
地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
イ 不燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな不燃性の管に収められていること。
六 それぞれの地中電線が、次のいずれかに該当するものである場合は、
地中電線相互の離隔距離が、0m以上であること。
イ 自消性のある難燃性の被覆を有すること。
ロ 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められていること。
(1) それぞれの地中電線が自消性のある難燃性の被覆を有する場合 (第125条1項6号イ)
(2) それぞれの地中電線が堅ろうな自消性のある難燃性の管に収められる場合 (第125条1項6号ロ)
(3) いずれかの地中電線が不燃性の被覆を有する場合 (第125条1項5号イ)
(4) 地中電線相互の間に危険を表示する埋設標識を設ける場合
(5) いずれかの地中電線が堅ろうな不燃性の管に収められる場合 (第125条1項6号ロ)
以上より、(4)が答えです。
問7.(3)
電気設備の技術基準の解釈 第224条【再閉路時の事故防止】
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に(ア)線路無電圧確認装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及び制御用電源 配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし、次のいずれかにより簡素化を図ることができる。
| イ | 2系列の保護リレーのうちの1系列は、(イ)不足電力リレー(2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。 |
| ロ | 計器用変流器は、(イ)不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。 |
| ハ | 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。 |
二
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
| イ | 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の(ウ)単独運転検出装置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 |
| ロ | 2方式以上の(ウ)単独運転検出装置(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 |
| ハ | 能動的方式の(ウ)単独運転検出装置及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい(エ)逆電力リレーを設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。 |
| ニ | 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき |
以上より、(3)が答えです。
問8.(4)
電気設備に関する技術基準を定める省令 第五十六条【配線の感電又は火災の防止】
配線は、施設場所の状況及び電圧に応じ、感電又は(ア)火災のおそれがないように施設しなければならない。
2 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による感電又は火災のおそれがないように施設しなければならない。
3 特別高圧の移動電線は、第一項及び前項の規定にかかわらず、施設してはならない。ただし、充電部分に人が触れた場合に人体に危害を及ぼすおそれがなく、移動電線と接続することが必要不可欠な電気機械器具に接続するものは、この限りでない。
電気設備に関する技術基準を定める省令 第六十六条
【異常時における高圧の移動電線及び接触電線における電路の遮断】
高圧の移動電線又は接触電線(電車線を除く。以下同じ。)に電気を供給する電路には、(イ)過電流が生じた場合に、当該高圧の移動電線又は接触電線を保護できるよう、(イ)過電流遮断器を施設しなければならない。
電気設備の技術基準の解釈 第171条3項【移動電線の施設】
高圧の移動電線は、次の各号によること。
一
電線は、高圧用の3種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
二
移動電線と電気機械器具とは、(ウ)ボルト締めその他の方法により堅ろうに接続すること。
三
移動電線に電気を供給する電路(誘導電動機の2次側電路を除く。)は、次によること。
| イ | 専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。 |
| ロ | 地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。 |
電気設備の技術基準の解釈 第171条4項【移動電線の施設】
特別高圧の移動電線は、第191条第1項第八号の規定により(エ)屋内に施設する場合を除き、施設しないこと。
⇩
電気設備の技術基準の解釈 第191条第1項第八号【電気集じん装置等の施設】
使用電圧が特別高圧の電気集じん装置、静電塗装装置、電気脱水装置、電気選別装置その他の電気集じん応用装置(特別高圧の電気で充電する部分が装置の外箱の外に出ないものを除く。以下この条において「電気集じん応用装置」という。)及びこれに特別高圧の電気を供給するための電気設備は、次の各号によること。
(第一号~第七号は省略)
八
移動電線は、充電部分に人が触れた場合に人に危険を及ぼすおそれがない電気集じん応用装置に附属するものに限ること。
以上より、(4)が答えです。
問9.(3)
電気設備の技術基準の解釈 第153条【電動機の過負荷保護装置の施設】
屋内に施設する電動機には、電動機が焼損するおそれがある過電流を生じた場合に(ア)自動的にこれを阻止し、又はこれを警報する装置を設けること。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
一
電動機を運転中、常時、(イ)取扱者が監視できる位置に施設する場合
二
電動機の構造上又は負荷の性質上、その電動機の巻線に当該電動機を焼損する過電流を生じるおそれがない場合
三
電動機が単相のものであって、その電源側電路に施設する(ウ)過電流遮断器の定格電流が15A((エ)配線用遮断器にあっては、20A)以下の場合
四
電動機の出力が(オ)0.2kW以下の場合
以上より、(3)が答えです。
問10.(5)
(1) 変流器は、一次電流から生じる磁束によって二次電流を発生させる計器用変成器である。
(2) 変流器は、二次側に開閉器やヒューズを設置してはいけない。
(3) 変流器は、通電中に二次側が開放されると変流器に異常電圧が発生し、絶縁が破壊される危険性がある。
(4) 変流器の通電中に、電流計をやむを得ず交換する場合は、二次側端子を短絡して交換し、その後に短絡を外す。
(5) 変流器は、一次電流が一定でも二次側の抵抗値により変流比は変化するので、電流計の選択には注意が必要になる。
赤線の部分が誤りですので、(5)が答えです。
問11.(a)(3)、(b)(1)
平成15年の問題13と同じ問題です。
(a)問題
河川流量\(Q[m^3/s]\)が流込式水力発電所の最大使用水量に等しくなるときの日数\(d\)が溢水が発生する日数の合計となるので、
\(Q=15=-0.05d+25\)
⇔\(d=200\)日
以上より、(a)問題は(3)が答えです。
発電に利用できる水量は、200日までは\(Q=15[m^3/s]\)、200日以降は直線的に減少していきますので、200日までの利用できる水量\(V_{200}\)と、200日以降で利用できる水量\(V_{365}[m^3]\)を分けて計算します。
・1~200日
\(V_{200}=15・3600・24・200=2.592×10^8\)
・200~365日
利用できる水量\(V_{365}\)は、縦軸の流量と横軸の日数の面積なので、台形の面積を求めれば水量が求まります。
\(V_{365}=\frac{1}{2}(15+6.75)[m^3/s]・3600[s]・24[h]・(365-200)[D]=1.550×10^8\)
したがって、年間で利用できる水量\(V[m^3]\)は、
\(V=V_{200}+V_{365}=4.142×10^8[m^3]\)
以上より、年間可能発電電力量\(P[GW・h]\)は、
\(P=9.8QHη_Tη_G=9.8・\frac{4.142×10^8}{3600}・20・0.9・0.95[kW・h]\)
⇔ \(P=19.3×10^6[kW・h]=19.3[GW・h]\)
以上より、(b)問題は(1)が答えです。
問12.(a)(4)、(b)(1)
(a)問題
電気設備の技術基準の解釈から、当該変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により、低圧電路の対地電圧が150Vを超えた場合に、自動的に高圧又は特別高圧の電路を遮断する装置を設ける場合、遮断時間に応じて必要なB種接地抵抗値は異なります。
| 遮断時間 | 接地抵抗値[Ω] |
|---|---|
| 下記以外の場合 | \(\frac{150}{I_g}\) |
| 1秒超~2秒以下 | \(\frac{300}{I_g}\) |
| 1秒以下 | \(\frac{600}{I_g}\) |
問題文の(ア)の条件から\(I_g=5[A]\)
問題文の(イ)の条件から、接地抵抗値は\(R_B=\frac{300}{I_g}=\frac{300}{5}=60[Ω]\)
以上より、(a)問題は(4)が答えです。
(b)問題
1線地絡電流\(I_g\)は、対地静電容量\(C\)と、接地抵抗\(R_B\)が直列接続された経路を通るのでその経路のインピーダンスは、
\(Z=R_B+\frac{1}{jω3C}=10+\frac{1}{j2π・50・3・0.1×10^{-6}}=10-j10615[Ω]\)
\(|Z|=\sqrt{10^2+10615^2}=10615[Ω]\)
接地抵抗にかかる電圧\(E[V]\)は、
\(E=\frac{200}{\sqrt{3}}=115.5[V]\)
常時流れる電流\(I_B[A]\)は、
\(I_B=\frac{E}{|Z|}=\frac{115.5}{10615}=10.88[mA]≒11[mA]\)
以上より、(b)問題は(1)が答えです。
問13.(a)(4)、(b)(3)
平成14年問題12と同じ問題です。
(a)問題
絶縁耐力試験の試験電圧(V[V]\)は、
\(V=6900×1.5=10350[V]\)
3線一括した高圧電路と大地との間の静電容量は\(0.2[μF]\)なので、絶縁耐力試験における対地充電電流\(I[A]\)は、
\(I=ωCV=2πfCV=2π・50・0.2×10^{-6}・10350=0.65[A]\)
以上より、(a)問題は(4)が答えです。
(b)問題
この試験に使用する試験装置に必要な容量\(Q[kV・A]\)は、
\(Q=VI=10350・0.65=6728[V・A]=6.728[kV・A]≒7[kV・A]\)
以上より、(b)問題は(3)が答えです。
令和6年度下期 科目リンク
出典元
一般財団法人電気技術者試験センター
令和6年度下期 第三種電気主任技術者試験 法規科目
関連省令
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)
参考書
イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。
問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。
問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。
本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。
この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。
ある程度学んで基礎がある人に向いています。
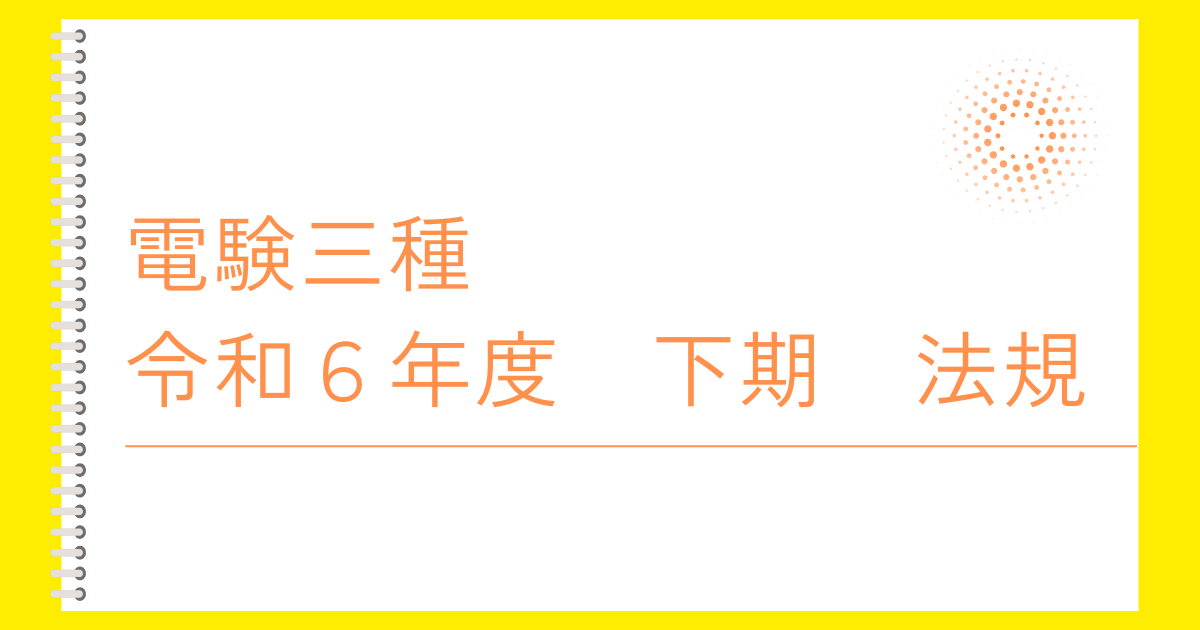
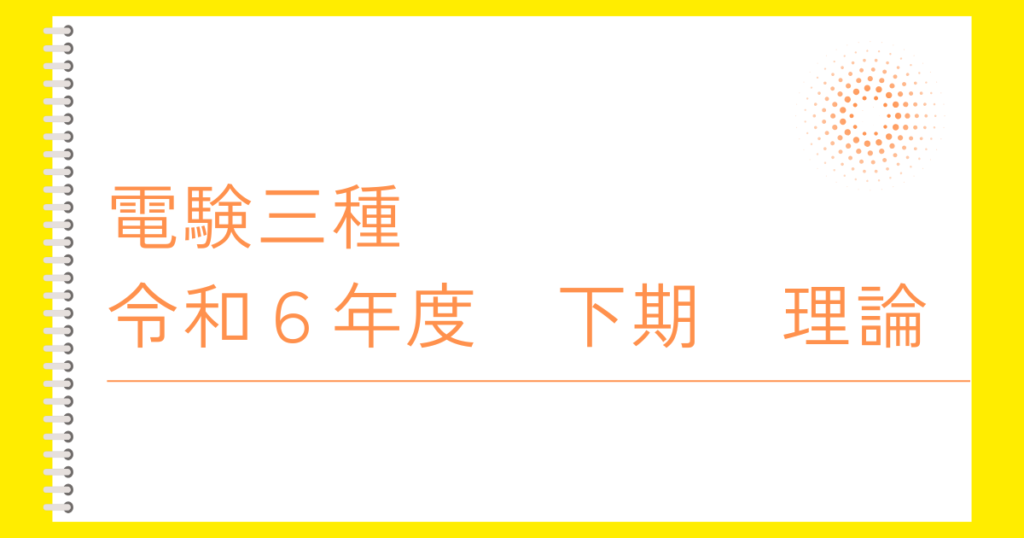
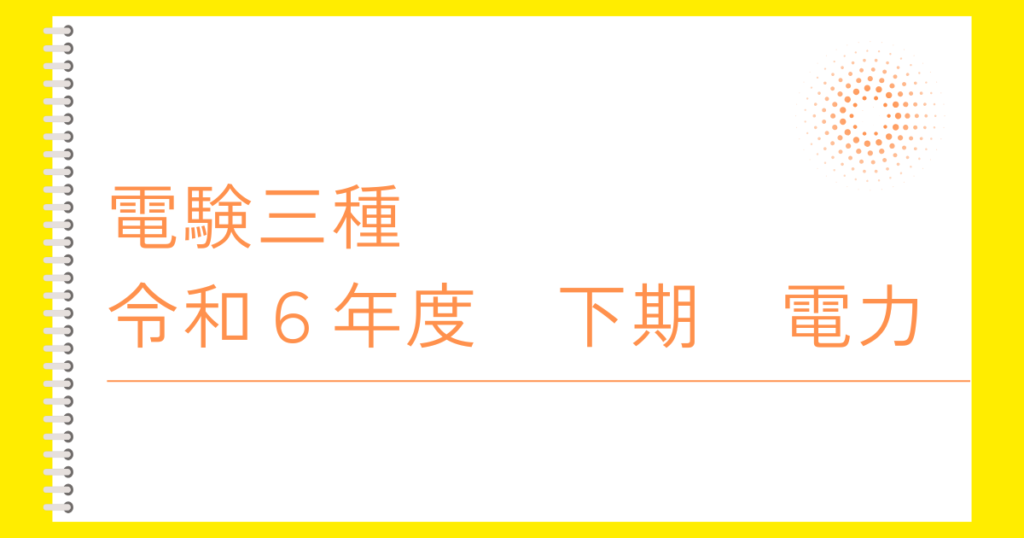
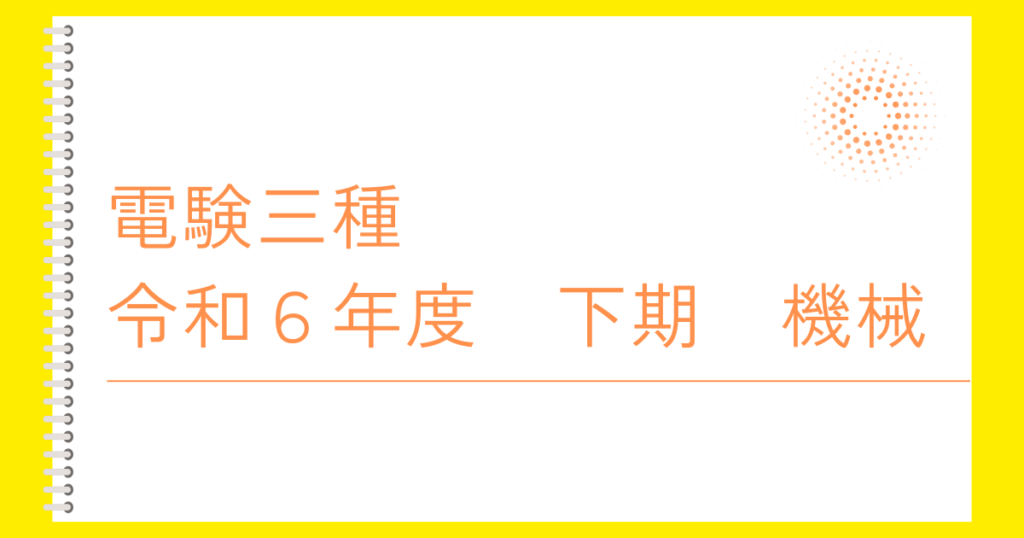
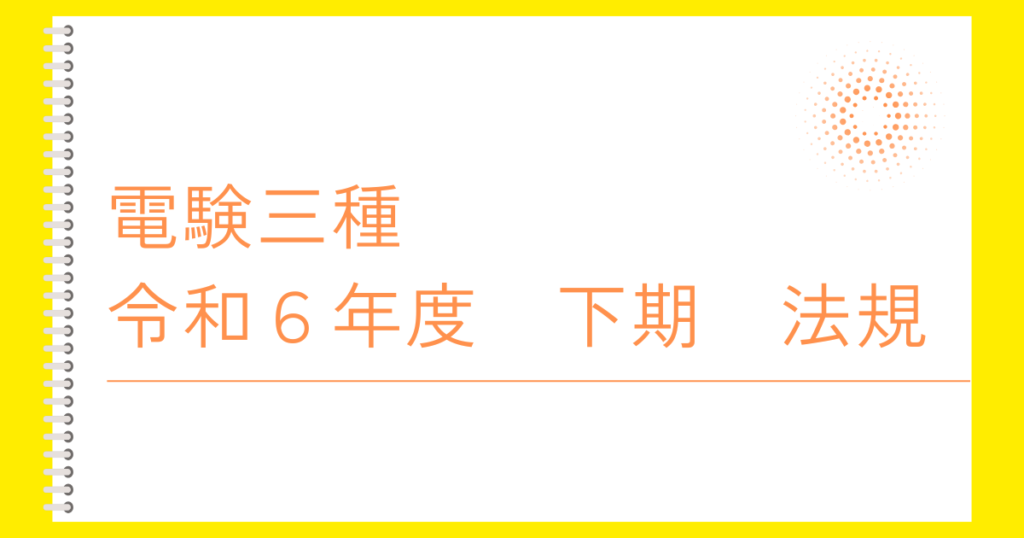
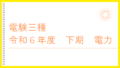
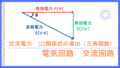
コメント