問1.(3)
発電電圧を主変圧器で昇圧する主変圧器には、発電機側にΔ結線、系統側にY結線のものが多く用いられます。
これは、2つのメリットがあるためです。
①変圧比を大きくとれる。②第3調波を系統側に流さない
なお、需要家で降圧する主変圧器では、系統側にY結線、負荷側にΔ結線のものが多く用いられます。
以上より、(3)が誤っています。
問2.(4)
給水加熱器は、ボイラーへ給水する水を加熱する熱交換器です。
抽気温度を上げるためではありません。
以上より、(1)が誤っています。
問3.(5)
衝動タービン
衝動タービンのノズルを通る間に蒸気の圧力が(ア)降下し、高速度となってノズルから噴出します。
羽根を通過する蒸気の通路の断面積が一様であり,羽根の出入口の蒸気の圧力は(イ)等しいです。
衝動タービンは蒸気圧力が(ウ)高圧のものに適します。
反動タービン
固定羽根で膨張させた蒸気を羽根に衝突させてランナを回転させるとともに,ランナの内部で蒸気を(エ)膨張させ、排気するときの反動力を利用してランナを回転させます。
反動タービンは,蒸気の圧力が(オ)中低圧のものに適します。
以上より、(5)が答えです。
問4.(1)
原子力発電の燃料にはウランが使用されており、ウラン235とウラン238が混ぜられています。
原子力発電所で使われている燃料は、核分裂しやすいウラン235を約4%、核分裂しにくいウラン238を約96%混ぜたものです。
以上より、(1)が誤っています。
問5.(3)
地熱発電は、地下から取り出した(ア)蒸気によってタービンを回して発電します。
発電に適した地熱資源は(イ)火山地域に多く存在します。
バイオマス発電は、植物や動物の(ウ)有機物から得られる燃料を利用します。
家畜の糞から作られる(エ)気体燃料も使われます。
以上より、(3)が答えです。
問6.(1)
調相設備は、負荷と(ア)並列に接続します。
電力用コンデンサは力率を(イ)進めるために用いられます。
分路リアクトルは力率を(ウ)遅らせるために用いられます。
同期調相機は、無負荷の同期電動機です。(エ)界磁電流を加減することによって、進み~遅れを連続的に調整できます。
静止形無効電力補償装置(SVC)は、(オ)半導体スイッチ(サイリスタ)でリアクトルをスイッチングし、連続可変量の無効電力を供給できます。
以上より、(1)が答えです。
問7.(4)
計器用変圧器、変流器は共に変圧器を使用して低電圧・小電流を取り出しています。
計器用変圧器は、1次巻線の巻き数が多く、2次巻線の巻き数が少ないため、低電圧を取り出せます。
計器用変流器は、1次巻線の巻き数が少なく、2次巻線の巻き数を多くすることで、小電流を取り出しています。
このことから、計器用変流器の二次端子には、常に(ア)低インピーダンス負荷を接続しなければなりません。
そして、二次回路を(イ)開放してはいけません。二次回路を開放すると、大きな(ウ)電圧が発生し、(エ)鉄損が過大となるため、変流器が故障します。
一次端子のある変流器は、その端子を被測定線路に(オ)直列に接続します。
以上より、(4)が答えです。
問8.(4)
碍子(がいし)の塩害対策として碍子洗浄、碍子表面の撥水物質の塗布はあります。
しかし、絶縁電線の採用は塩害対策として使用しません。
以上より、(4)が答えです。
問9.(4)
高圧配電線路は、1線地絡電流を(ア)小さくするため、(イ)非接地方式が採用されています。
地絡保護には地絡方向継電器(DGR)が一般的に使用されております。
DGRは、電圧の位相と、地絡電流の位相を比較することで、保護対象の回路で地絡が発生したか、対象外の回路で地絡が発生したかを判別しています。
保護対象の回路で地絡が発生した場合、電圧の位相と地絡電流の位相は合います。しかし、対象外の回路で地絡が発生した場合、電流の向きが逆向きになるため、電圧の位相と地絡電流の位相が(ウ)逆位相となります。
短絡故障が発生した際の保護装置として、(エ)高圧カットアウト(PCS)があります。
これは、変圧器保護に使用されるため、柱状変圧器の(オ)一次側に接続されます。
以上より、(4)が答えです。
問10.(3)
ケーブルの相電圧\(E=\frac{V}{\sqrt{3}}=3810[V]\)
こう長2kmのケーブルの心線1線当たりの静電容量\(C[F]\)は、
\(C=2×0.5×10^{-6}=10^{-6}[F]\)
この静電容量に流れる電流\(I[A]\)は、
\(V=\frac{I}{2πfC}\)
⇔\(I=2πfCE\)
1線当たりの無負荷充電容量\(Q[kV・A]\)は、
\(Q=2πfCE^2=2π・60・10^{-6}・3810^2=5.471[kV・A]\)
3線の無負荷充電容量\(Q_3[kV・A]\)は、
\(Q_3=3Q=3・5.471≒16.4[kV・A]\)
以上より、(3)が答えです。
問11.(3)
遮断器は、送電線路の運転・停止、故障電流の遮断などに用いられますので、(3)は目的が異なります。
問12.(2)
三相電力の式から、電流\(I[A]\)を求めます。
\(P=\sqrt{3}V_rIcosθ\)
⇔\(I=\frac{P}{\sqrt{3}V_rcosθ}\)
3線の電力損失\(P_L\)は、
\(P_L=3I^2R=\frac{RP^2}{(\sqrt{3}V_rcosθ)^2}\)
電力損失率\(\frac{P_L}{P}\)は、
\(\frac{P_L}{P}=\frac{RP}{(\sqrt{3}V_rcosθ)^2}\)
以上より、(2)が答えです。
問13.(3)
平成24年問13と同じ内容です。
導体の温度が30℃のときの電線の長さ\(L_{30}\)は、
\(L_{30}=S+\frac{8D^2}{3S}=100+\frac{8・2^2}{3・100}=100.1067[m]\)
60℃のときの電線の長さは、線膨張係数\(α=1.5×10^{-5}\)を使い、
\(L_{60}=L_{30}(1+α(t_{60}-t_{30})=100.1067(1+1.5×10^{-5}(60-30))\)
\(L_{60}=100.1067・1.00045≒100.1517[m]\)
導体の温度が60℃になったときのたるみを\(D_{60}\)とすると、
\(L_{60}=S+\frac{8D_{60}^2}{3S}=100+\frac{8D_{60}^2}{3・100}=100.1517\)
⇔\(D_{60}=\sqrt{\frac{3・100・(100.1517-100)}{8}}≒2.39[m]\)
以上より、(3)が答えです。
問14.(4)
軟銅線は、硬銅線を焼きなまして発生する残留応力を除去してしなやかにするため、可とう性がよくなります。焼きなましとは、加熱してから徐々に冷却処理する処理です。
軟銅線は、硬銅線よりも導電率が高くなるため、(4)は間違いです。
問15.(a)(4)、(b)(3)
(a)問題
熱量Jと、仕事率Wの関係は、1[W]=1[J/s]なので、1時間当たりの熱量は、[J/h]=3600[W]です。
それを踏まえ、火力発電所の出力が1000MWであることから、1時間あたりの発電に必要なエネルギー量\(P[GJ/h]\)は、
\(P=\frac{1000}{0.41}・3600=8780[GJ/h]\)
重油発熱量が
\(Q=44000[kJ/kg]=44000[MJ/t]=44[GJ/t]\)
1時間当たりの重油消費量を\(V[t/h]\)とすると、
\(V=\frac{P}{Q}=\frac{8780}{44}=199.56≒200[t/h]\)
以上より、(a)は(4)が答えです。
(b)問題
1日に消費する重油量\(V_D\)は、
\(V_D=24V_h=24・199.56=4789.44[t]\)
消費した重油に含まれる炭素の量\(V_C\)は、炭素の重量比が85%であることから
\(V_C=0.85V_D=4071[t]\)
炭素の原子量は問題文から12。
二酸化炭素\(CO_2\)の原子量は、\(12+16×2=44\)です。
このことから、1日に発生する二酸化炭素の重量\(V_{CO2}\)は
\(V_{CO2}=V_C・\frac{44}{12}=14927=14.9×10^3≒15×10^3\)
以上より、(b)は(3)が答えです。
問16.(a)(3)、(b)(4)
(a)問題
負荷を流れる電流\(\dot{I_r}=400A\)は、力率が\(cosθ_r=\frac{\sqrt{3}}{2}=0.866\)なので、
\(\dot{I_r}=400(cosθ_r-jsinθ_r)=400(0.866-j0.5)=346.4-j200\)
力率が遅れであるため、\(jsinθ_r\)の項はマイナスです。
T型回路の右側のインピーダンス\(\frac{\dot{Z}}{2}\)は、
\(\frac{\dot{Z}}{2}=10+j40\)
\(\dot{V_c}\)は、
\(\dot{V_c}=\dot{V_{r1}}+\dot{I_r}\frac{\dot{Z}}{2}\)
⇔\(\dot{V_c}=150000+(346.4-j200)(10+j40)=161464+j11856\)
\(\dot{V_c}\)の大きさ\(|V_c|\)は、
\(|V_c|=\sqrt{161464^2+11856^2}=161899[V]=161.9[kV]\)
以上より、(a)は(3)が答えです。
(b)問題
アドミタンスに流れる電流\(\dot{I_c}\)は、
\(\dot{I_c}=\dot{V_c}・Y=(161464+j11856)・j0.0007=j113.0-8.3[A]\)
送電端の電流\(\dot{I_s}\)は、
\(\dot{I_s}=\dot{I_r}+\dot{I_c}=346.4-j200-j8.3+j113.0=338.1-j87\)
送電端電圧\(\dot{V_{s1}}\)は、
\(\dot{V_{s1}}=\dot{V_c}+\dot{I_s}・\frac{\dot{Z}}{2}\)
\(\dot{V_{s1}}=161464+j11856+(338.1-j87)(10+j40)=168325+j24510\)
送電端電圧の大きさ\(|V_{s1}|\)は、
\(|V_{s1}|=\sqrt{168325^2+24510^2}=170100[V]=170.1[kV]\)
以上より、(b)は(4)が答えです。
問17.(a)(2)、(b)(4)
(a)問題
送電端の相電圧\(E_s\)は、
\(E_s=\frac{V_s}{\sqrt{3}}=\frac{66000}{\sqrt{3}}=38106[V]\)
送電端から、送電線路を通り、受電端のアドミタンスを通って電流が地面に流れます。
その経路のインピーダンスを\(Z\)としたとき、
\(Z=jX+\frac{2}{jB}=j200-j2500=-j2300[Ω]\)
このインピーダンスを流れる電流を\(I_r\)としたとき、
\(I_r=\frac{E_s}{Z}=\frac{38106}{-j2300}=j16.57[A]\)
送電端と受電端の電位差\(E_{sr}\)は、
\(E_{sr}=jX・I_r=j200・j16.57=-3314[V]\)
したがって、受電端の相電圧\(E_r\)は、
\(E_r=E_s-E_{sr}=38106-(-3314)=41420[V]\)
受電端の線間電圧\(V_s\)は、
\(V_r=\sqrt{3}E_r=\sqrt{3}・41420=71739=71.7[kV]\)
以上より、(a)は(2)が答えです。
(b)問題
送電端のアドミタンスに流れる電流を\(I_s\)としたとき、
\(I_s=j\frac{B}{2}・E_s=j0.4×10^{-3}・38106=j15.2[A]\)
したがって、送電端を流れる電流\(I[A]\)は、
\(I=I_s+I_r=j15.2+j16.57=j31.77≒j31.8[A]\)
以上より、(b)は(4)が答えです。
令和6年度下期 科目リンク
出典元
一般財団法人電気技術者試験センター
令和6年度下期 第三種電気主任技術者試験 電力科目
参考書
イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。
問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。
問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。
本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。
この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。
ある程度学んで基礎がある人に向いています。
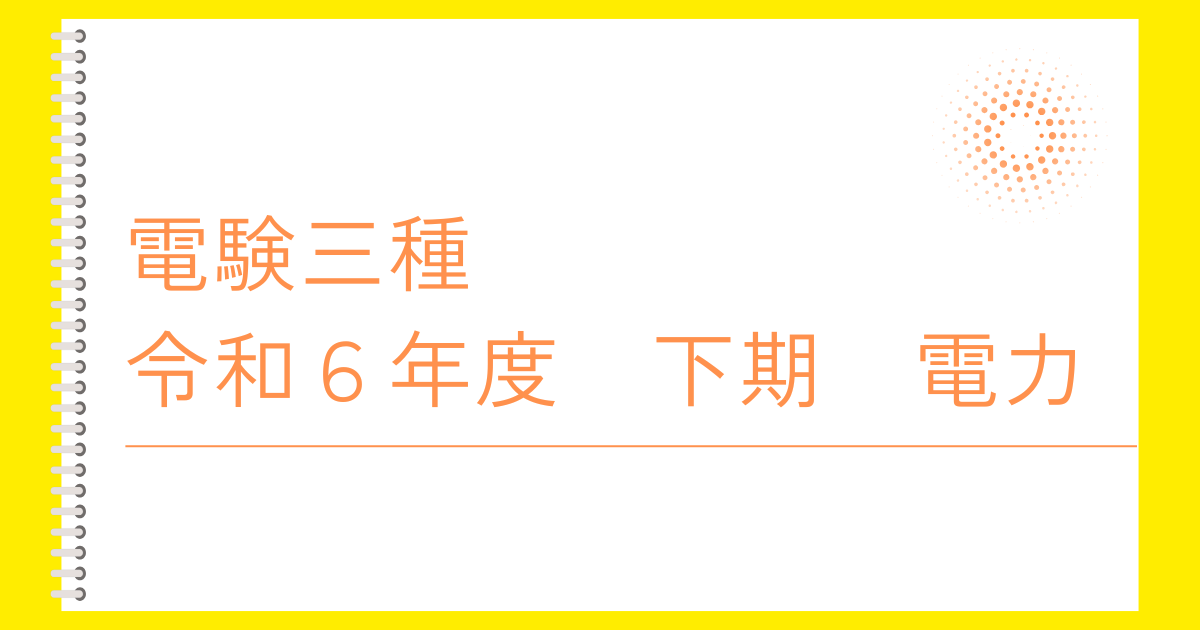
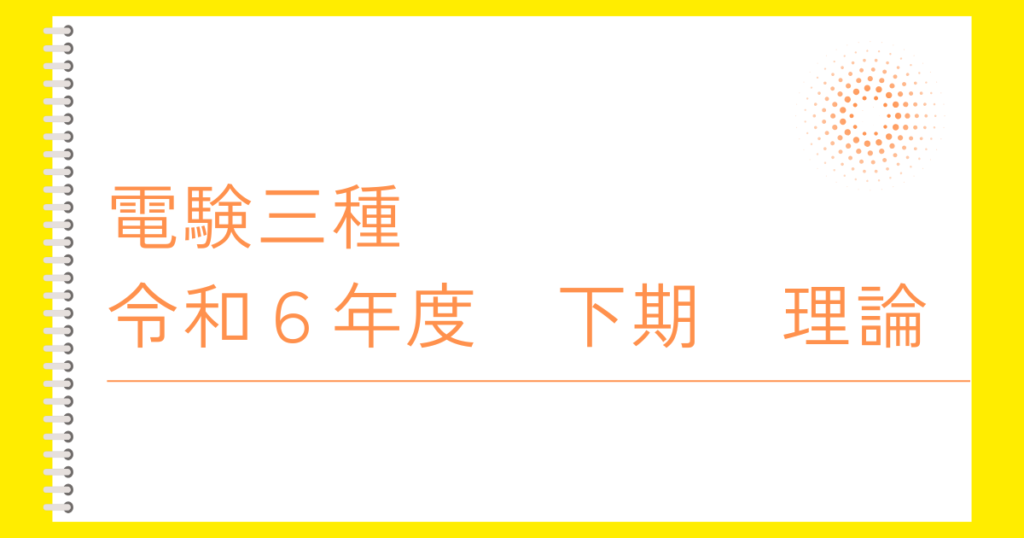
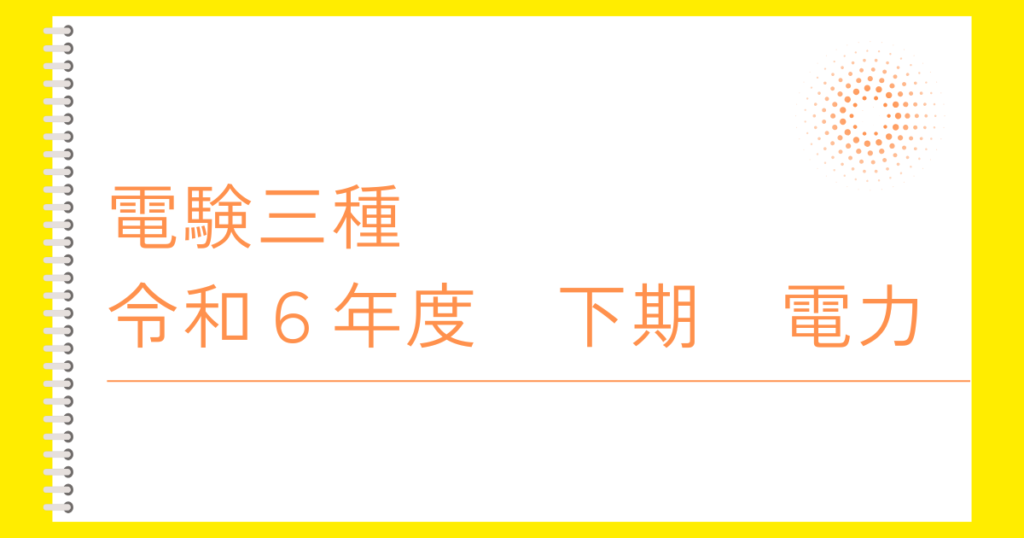
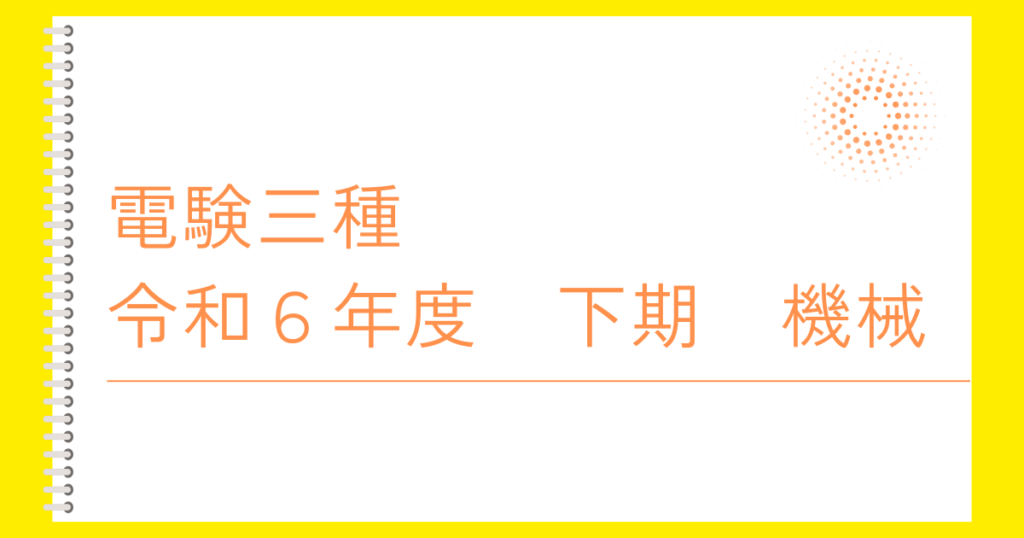
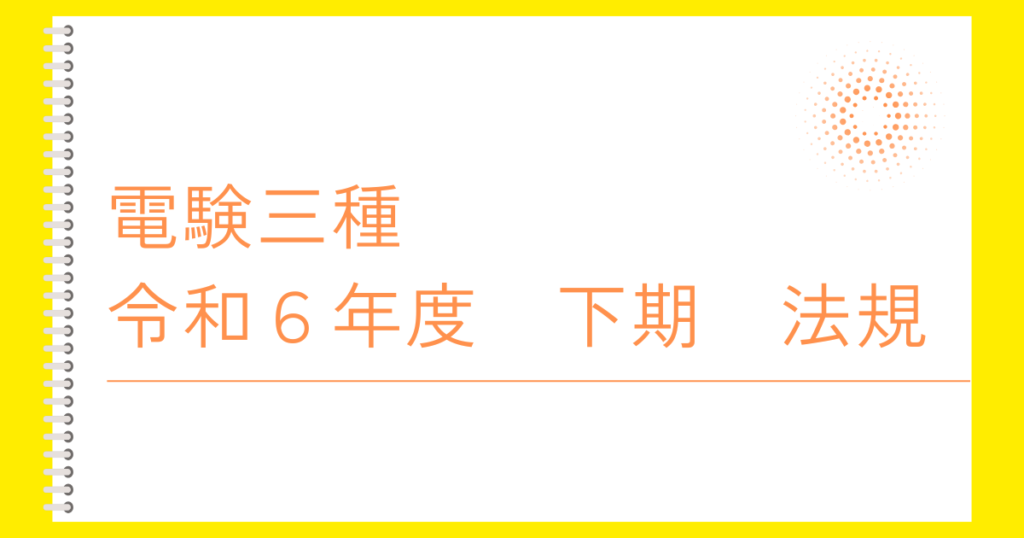
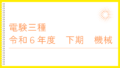
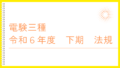
コメント