ADCの概要
アナログデジタル変換器(Analog Digital Converter)は、ADCと呼ばれ、アナログ信号をデジタル信号に変換する変換器です。
ADCは、フラッシュ型、逐次比較型、パイプライン型、ΔΣ型、二重積分型等の様々な種類の方式があり、方式によって周波数帯域(変換速度)、分解能(変換精度)が異なります。
本頁では、二重積分型ADCについて解説します。
二重積分型ADC
測定原理
入力信号\(V_{in}\)を一定時間\(T_{in}\)秒間、積分器で積分し、積分器の出力電圧が\(V_{sig}\)となります。
次に、基準電圧\(V_{ref}\)を積分します。\(V_{sig}=0V\)となって比較器が反転するまでの時間を\(T_{ref}\)秒とします。
基準電圧\(V_{ref}\)と、測定した時間\(T_{in},T_{ref}\)から、測定対象の電圧\(V_{in}\)が
\(\displaystyle V_{in}=\frac{T_{ref}}{T_{in}}V_{ref}\)
と計算されます。
長所
周波数が低い信号の測定精度が高い。特に、直流電圧の精密な測定に向いている。
短所
測定できる信号の周波数は低く、数百Hz程度までしか測定できない。
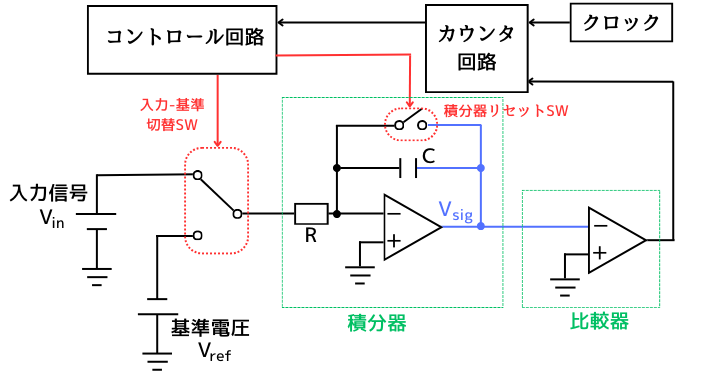
回路動作の流れ
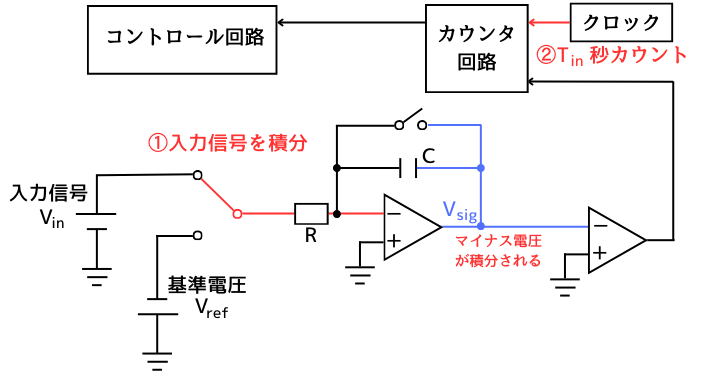
①測定したい入力信号\(V_{in}\)を積分器に入力する。
②\(T_{in}\)秒の時間経過をカウンタ回路で数える。
→
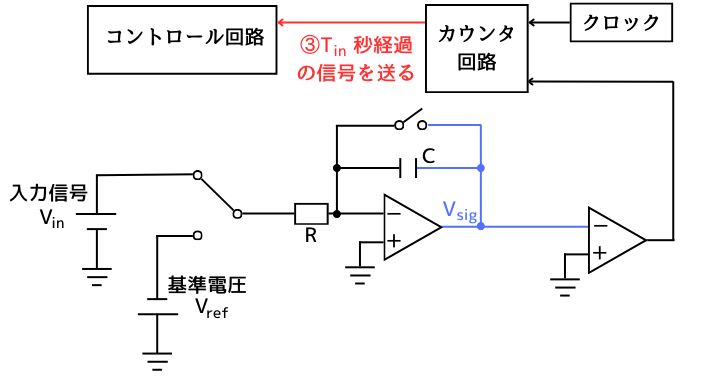
③\(T_{in}\)秒経過後、カウンタ回路からコントロール回路に、時間経過したことを知らせる信号を送る
↙
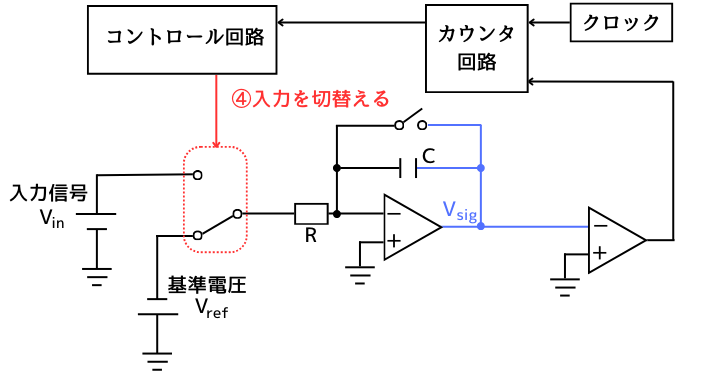
④コントロール回路が、入力スイッチを切替える
→
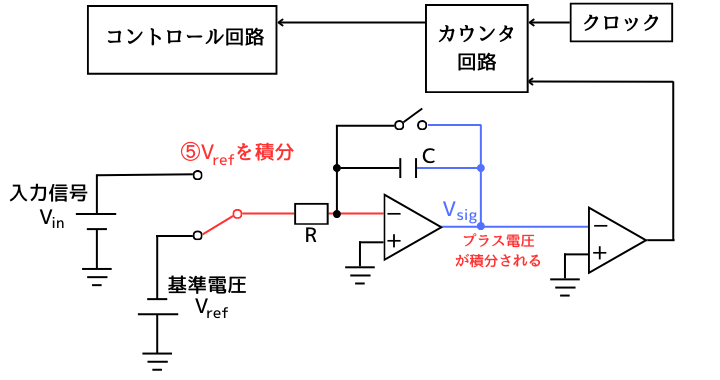
⑤逆電圧の基準電圧\(V_{ref}\)を積分器に入力して逆積分を開始する。
↙
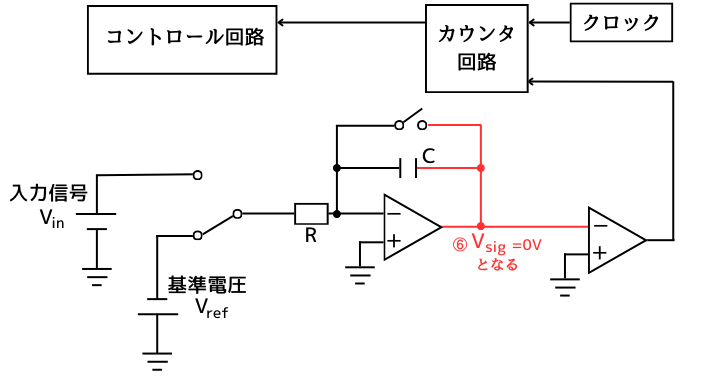
⑥積分器の出力電圧が\(V_{sig}=0\)となる。
→
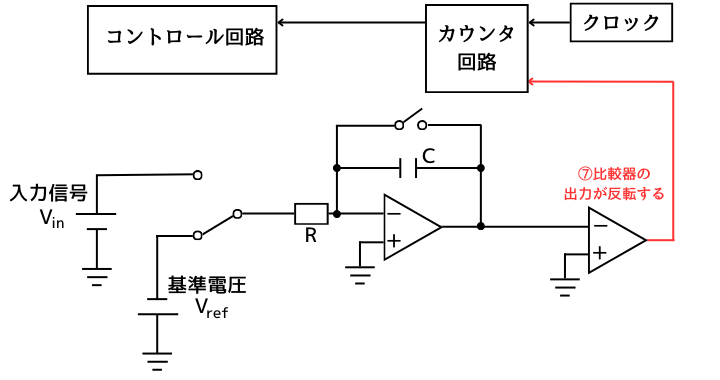
⑦\(V_{sig}≧0\)となることで、比較器の出力が反転する。
↙
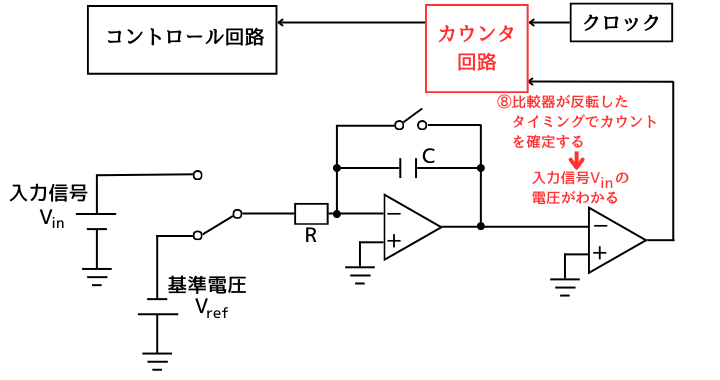
⑧カウンタ回路が、比較器からの反転出力を受け取ることで、測定が完了する。
入力信号の電圧が
\(\displaystyle V_{in}=\frac{T_{ref}}{T_{in}}V_{ref}\)
と、求まる。
→
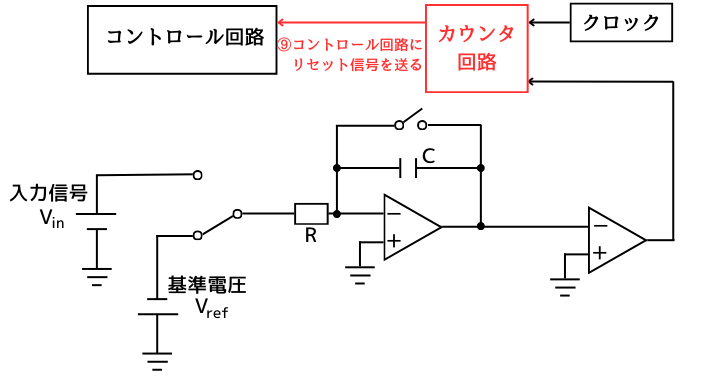
⑨測定完了のため、コントロール回路に回路状態を初期化する操作をするための信号を送る
↙
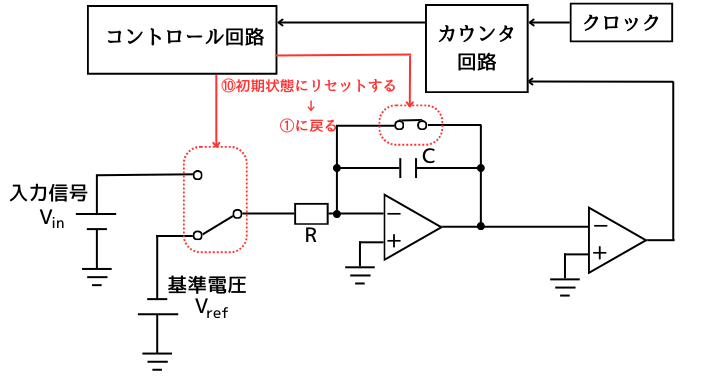
コントロール回路が、回路状態を初期化する。その後、①に戻る。
測定値の計算
積分器の出力は、次のグラフのように変動します。
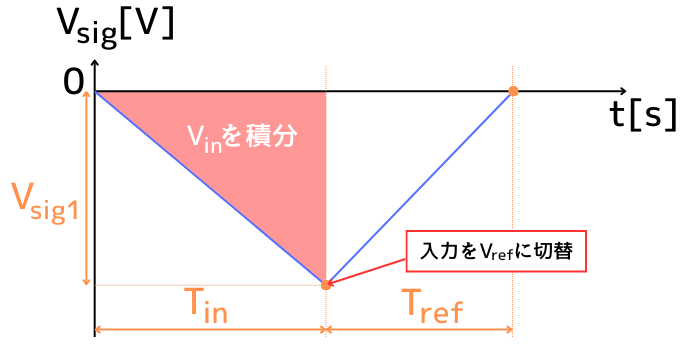
最初に、入力電圧\(V_{in}\)を積分したとき、入力電圧は+電圧であるため、反転して-電圧が積分されていきます。
積分器の出力電圧\(V_{sig}\)は、
\(\displaystyle V_{sig}=-\frac{V_{in}}{CR}t\)
です。
\(T_{in}\)秒積分した結果の積分器の電圧\(V_{sig1}\)は、次のように求まります。
\(\displaystyle V_{sig1}=-\frac{V_{in}}{CR}T_{in}\)
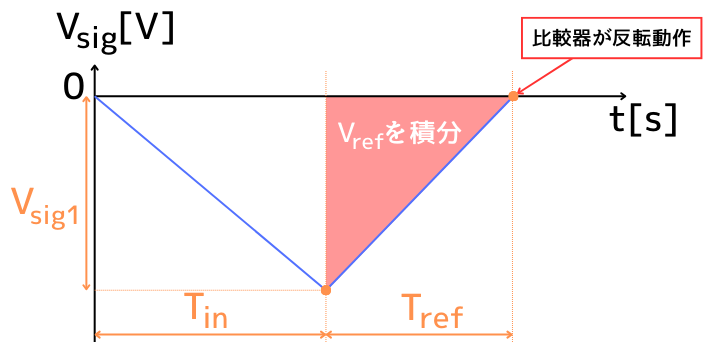
次に、基準電圧\(-V_{ref}\)を積分します。基準電圧は-電圧であるため、反転して+電圧が積分されていきます。
初期電圧は\(V_{sig1}\)なので、積分器の出力は次式となります。
\(\displaystyle V_{sig}=V_{sig1}+\frac{V_{ref}}{CR}t\)
\(T_{ref}\)秒積分したとき、\(V_{sig}=0\)となり、比較器が反転動作して測定が完了します。
この時の\(V_{sig}\)から\(V_{in}\)を求めることができます。
\(\displaystyle V_{sig}=V_{sig1}+\frac{V_{ref}}{CR}T_{ref}=0\)
➡ \(\displaystyle 0=-\frac{V_{in}}{CR}T_{in}+\frac{V_{ref}}{CR}T_{ref}\)
➡ \(\displaystyle \frac{V_{in}}{CR}T_{in}=\frac{V_{ref}}{CR}T_{ref}\)
➡ \(\displaystyle V_{in}=\frac{T_{ref}}{T_{in}}V_{ref}\)
関連記事(その他)
参考書
イラストがとても多く、視覚的に理解しやすいので、初学者に、お勧めなテキストです。
問題のページよりも、解説のページ数が圧倒的に多い、初学者に向けの問題集です。
問題集は、解説の質がその価値を決めます。解説には分かりやすいイラストが多く、始めて電気に触れる人でも取り組みやすいことでしょう。
本ブログの管理人は、電験3種過去問マスタを使って電験3種を取りました。
この問題集の解説は、要点が端的にまとまっていて分かりやすいのでお勧めです。
ある程度学んで基礎がある人に向いています。
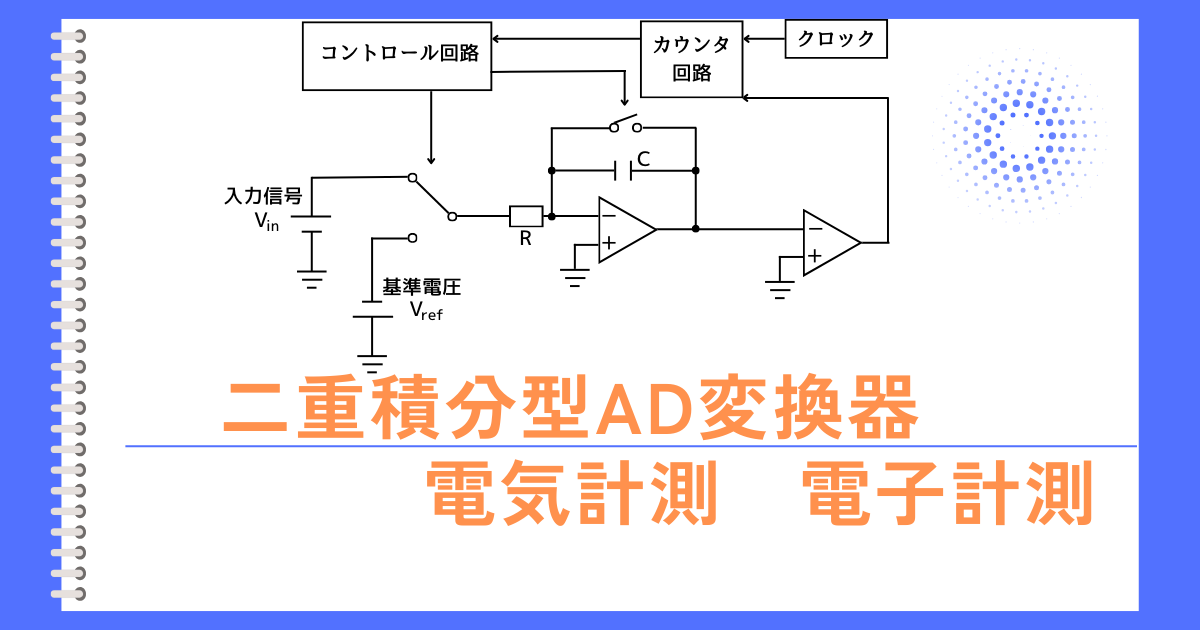
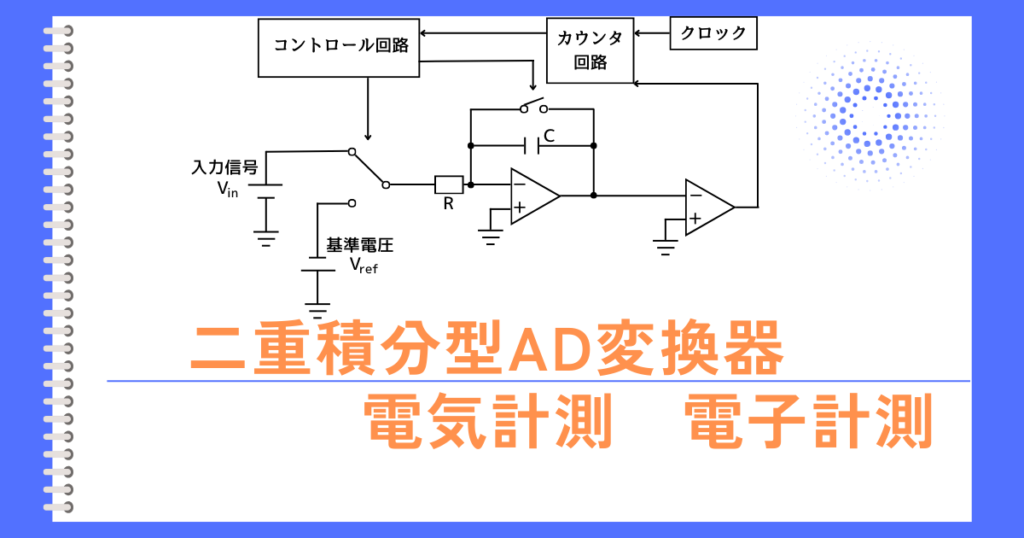


コメント